~湘南慶育病院副院長・脳神経センター長の寺山靖夫先生の講話から~
こんにちは。
少し前になるのですが、湘南慶育病院さんが開催された「地域連携会」に参加してきました。
その中で、副院長で脳神経センター長の寺山靖夫先生による「知っておきたい認知症の知識」という講話を聴くことができたのですが、本当に心に響く、素晴らしいお話でした。
「この感動をぜひ皆さんとシェアしたい!」と思ったので、今日はその時のことをレポートします。
認知症と聞くと、少し難しいイメージや、不安な気持ちになる方もいるかもしれません。
でも、寺山先生のお話は、そんな私たちの心にそっと寄り添ってくれるような、温かくて、そして「なるほど!」と思える発見に満ちたものでした。
そもそも「認知症」ってなんだろう?
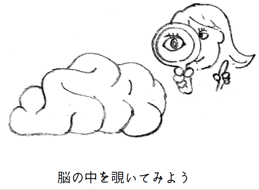
寺山先生は、認知症を「脳の老化による病気」と、とても分かりやすく説明してくださいました。
年を重ねると身体のあちこちが変化するように、脳も少しずつ変化していきます。その変化によって脳の中のバランスが少しずつ崩れていき、日々の生活に支障が出てくる状態が認知症だそうです。
日本では2025年、つまり今年中には、65歳以上の方の約5人に1人が認知症になると言われています。もう、誰にとっても他人事ではないのですね。
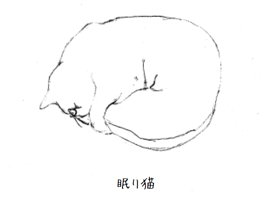
そして、先生が特に強調されていたのが「睡眠」の大切さ。
質の良い睡眠をとっている間に、脳は日中に溜まった「ゴミ(アミロイドという老廃物)」をお掃除してくれるのだそうです!
睡眠不足は、このお掃除の時間を奪ってしまうことに…。
ぐっすり眠ることが、脳の健康にとっていかに大切か、改めて実感しました。
心のサイン「BPSD」と、私たちにできること
認知症の方に見られることがある、妄想や徘徊、不安といった行動や心理状態の変化。これを「BPSD」と呼ぶそうです。
これを聞くと、「ご本人の性格が変わってしまったのかな?」と思いがちですよね。
でも、先生はこうおっしゃいました。
「BPSDの原因の約9割は、周りの環境にあるのですよ。」
つまり、ご本人のせいではなく、周りの人の対応や生活の変化が、心のサインとして現れていることが多い、ということです。これには、本当にハッとさせられました。
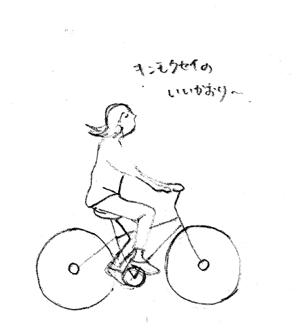
では、私たちはどう向き合えば良いのでしょうか?
先生が教えてくれた大切なヒントは次の3つです。
- プライドを傷つけない:何よりも一番大切なこと。一人の人間として尊重する気持ちを忘れないようにしたいですね。
- 話をじっくり聞く:ご本人は、私たちには分からない不安や焦りを抱えているかもしれません。その気持ちに、ただただ耳を傾けることが、安心につながるのですね。
- 「いつもと違う日」を作ってみる:イライラしやすい(易刺激性)のは、何かきっかけがあるはず。毎日同じことの繰り返しではなく、少しだけ環境に変化をつけることで、ご本人の気持ちが和らぐこともあるそうです。
介護する人も、自分を大切に

先生は、介護するご家族の負担にも、温かい視線を向けていました。
特に、介護の中で「ご家族が眠れているか」「ご本人のトイレの様子に変化はないか」という2点は、介護の負担を測る上でとても重要なサインになるとのこと。
介護は一人で抱え込むものではありません。
ご家族自身が健やかでいることが、結果的にご本人にとっても一番良い環境に繋がるのですね。
寺山先生からの、心に響くメッセージ
講演の最後に、寺山先生が語ってくださった言葉が、今も胸に残っています。
認知症の方を病人と考えるのは無理なことです。
認知症であっても、社会の一員であることに何ら変わりはないのです。
認知症であっても、人間としての感情→嬉しい・楽しい・辛い・苦しいなど
脳の奥深くに存在する人間として大切な感情は決してぶれることはありません。
認知症は、その人の一部ではあっても、その人の全てではありません。嬉しい、楽しい、そして辛いといった感情は、私たちと何も変わらない。
その当たり前のことを、私たちはつい忘れてしまいがちです。
寺山先生のお話を聞いて、認知症というものを正しく理解し、一人の人間として向き合うことの大切さを改めて感じました。
この温かい先生のメッセージが、一人でも多くの方の心に届けば嬉しいなと思いました。
スタッフ8号(イラスト:スタッフ2号)


